いつまで続く? 生命保険法人契約の税務に関わるイタチごっこ

2月14日、「全損型保険、販売停止!」報道が各紙を飾った。取上げ方は、概ね同様である。すなわち、ここ数年、大量販売となっていた節税商品「全損型保険」を国税・金融庁が問題視。生保各社が販売を停止したとの報道である。しかし、この商品単体を停止すれば問題が根本的に解消するのだろうか?
生命保険法人契約に関わる税務上の規定や解釈の変更は、今まで幾度か行われてきた。直近では平成24年4月27日付でがん終身保険に関わる法令解釈通達が出されている。それ以前では平成20年2月28日付逓増定期保険に関わる改定がある。
その後落ち着いて現在に至っていると考えていたが、冒頭触れたようにここにきて動きだしそうな状況である。しかし現時点で全損型保険が問題視された事実以上の話はなく、新たな税務取り扱いの改定方針が出されたわけでもない。そこで過去の改定の背景にある根本的な要因と、それをかいくぐるような生保商品の登場、その結果行われる税務上の規定や解釈変更のイタチごっこを考えてみたい。
1 税務会計の基本的考え方
ここで一旦、我々は保険税務から離れよう。すなわち、まず企業における税務会計の基本となる考え方を確認しておくこととしたい。税務会計の基本となる考え方は極めてシンプルである。すなわち「長期の前払費用は資産計上」である。当該事業年度において役務の提供を受けていない部分で1年以上の期間にわたる長期の前払い費用は、固定資産に計上される。これが原則である。
2 生命保険における平準保険料と保険税務
さて、それでは生命保険の場合はどうだろうか? 長期平準定期保険を考えてみよう。100歳満了の当該保険に50歳男性が保険金1億円で加入した。全期払の年払保険料は280万5600円(ある会社の例)である。50歳で加入するとその後、毎年同じ保険料を納める。さて死亡保険金が1億円なので、死亡すれば1億円が保険金として支払われる。加入後1年であろうが20年後であろうが、死亡すれば1億円が支払われる。
次に死亡率をみてみよう。生保標準生命表2018(死亡保険用)の抜粋が図表1である。
図表1 生保標準生命表2018(死亡保険用)男性50歳~100歳(筆者が抜粋して作成)
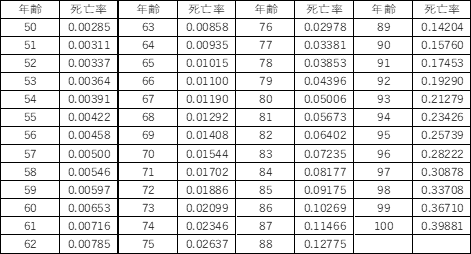
50歳男性が10万人いれば死亡率から285人が死亡する計算になる。同様に60歳では653人、70歳では1544人、年齢が高いほど死亡率は高い。死亡率が毎年上昇するのに対して保険料は毎年同額である。ここで見ているケースでいうと50歳から100歳満了に至るまでの死亡率を平準化して保険料を算出しているために、毎年同額の保険料となっている。これを平準保険料という。
もともと平準保険料方式をとっているということは、将来の死亡保障のための前払い部分がそこには存在している。期間10年の定期保険でも、100歳満了の長期平準定期保険でも、それぞれの設定条件により前払い保険料が織り込まれている。
したがって、税務会計の考え方からいえば、その契約ごとに適切に長期の前払い部分を資産に計上する必要がある。ところが保険の場合、その情報を加入している側は持っていない。保険会社もそれらを開示していないし、開示するとしたら設定条件によって相違するから事務的な負荷を考えても合理的でない。そこで簡便法として保険に関する税務通達が発出されており、それに沿って処理することになる。
定期保険については以下の通りとなっている。
「(定期保険に係る保険料)
9-3-5 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、傷害特約等の特約が付されているものを含む。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(傷害特約等の特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2-15「十三」により追加、昭59年直法2-3「五」により改正)
(1) 死亡保険金の受取人が当該法人である場合 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。((2)以下省略)」
ここでの定期保険は毎年の保険料と対価としての保障という便益とが対応関係をもって期間を経過していくと想定されている。だからこそ保険料は、死亡保険金の受取人が法人であっても損金に算入される。
ところが、この定期保険の期間を延ばして長期にしていくと、契約期間の最初から最後まで一律に損金算入することが不適切なほど前払い保険料が多くなる。そこで定期保険と長期平準定期保険に区分する考え方が導入された(昭和62年)。
「保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるもの」これが長期平準定期保険ということになる。
長期平準定期保険に区分されると、契約当初6割期間、保険料(全期払)の1/2が損金算入されることになる。これはその期間、それだけ保険料に占める前払い部分が多いと考えられたことによる。細かく見れば加入年齢等によって前払い保険料の構成は相違するが、簡便法としてそのように処理することとしたわけである。
次に保険期間だけでなく、契約当初の保険金が一定期間経過後に増加するような商品が出てくると、これも上記の保険期間だけで割り切ることができなくなる。これが逓増定期保険である。逓増定期保険は、保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるものをいう。
この商品については平成8年に規定された後、(想定より前払い保険料部分が多いと認識されたため)平成20年2月28日付で更に改定された。内容的には保険期間満了時の被保険者の年齢範囲により、契約当初の6割期間について1/2損金、1/3損金、1/4損金の3通りに区分されている。
同様の主旨で平成24年にがん終身保険の法令解釈通達が出されている。これもそれ以前は、がん終身保険全期払については、保険料を全額損金に算入していた。ところが解約返戻金が高額に生じることから、前払い保険料が相当程度あると認識され、計算上の保険期間(105歳までの期間)の50%相当期間を前期期間として保険料の1/2を損金とする改定が行われた。
3 これまでの経緯と現状
これまでの経緯をみると、以下のように整理できそうである。すなわち、簡便法としての通達等による処理と、実際の保険商品における前払い保険料部分の構成に乖離が生じ、保険料の損金算入割合と解約返戻金の生じ方にバランス上問題ありと認識されると当該保険税務に関わる変更等が行われる。
さて、そこで今度は、問題視されている話に移ろう。 最近の売れ筋商品としてやり玉に挙がっている「一定期間災害保障重視型定期保険」である。
この保険は、保険期間を二つに分け、前期期間を災害保障のみとし死亡保険金を設定しない(病気死亡の場合は責任準備金相当額を保障)。基本保険金1億円、50歳男性77歳満了、前期期間10年の場合、全期払の年払保険料は256万6300円である(ある会社の例)。前期期間において死亡保険金がないが、分類上はあくまで「定期保険」なので、税務上の解釈は「法人税法基本通達9-3-5」及びその後の「平成20年2月28日課法2-3、課審5-18により改正」に基づいて行われている。
この通達等における「定期保険」は、契約当初に保険金が設定され、保険期間として長期に該当するか、該当しないかによって定期保険・長期平準定期保険に区分される。また、一定の期間条件の上で、当初保険金が保険期間の経過に応じて逓増するものを逓増定期保険とする。内容的に見て(一定期間災害保障重視型定期保険のように)保険金が契約当初から一定の期間(前期期間)設定されず、その経過後に保険金が設定されるような商品を織り込んでこれら通達等が考えられたとは到底考えられない。
一定期間災害保障重視型定期保険は、構造的に逓増定期保険に似ている。すなわち、契約当初と後半で比べた場合、死亡保障が「契約当初<契約の後半」となっており、それだけ契約始期から一定期間、保険料における前払い部分が大きいという点である。
逓増定期保険は、契約期間の進行とともに保険金を増加させた商品である。これに対して、一定期間災害保障重視型定期保険は、逓増定期保険と逆に、前半期間について保険金をなくしてしまった商品と見ることもできる。その結果、死亡保障が「当初<後期」という同じ状態を作り出している。それにもかかわらず、保険期間の設定のみによって「定期保険」に区分されれば全額損金可能と解釈されている。上記の契約例では、全額損金算入可能とされ、かつ経過10年段階の解約返戻率は85.6%程度となっている。
現行の税制の盲点を突くような保険会社の商品開発には驚くが、税務上の通達等の背後にある考え方をまともに適用すれば、このような扱いが維持できるとは考えにくい。
根本的な問題の背景は、税務における期間損益の考え方と平準保険料方式をとる生命保険の矛盾と折り合いである。この矛盾を突いて極端に前払い保険料を増大させた商品が開発、販売されれば、その時点の保険税務に関わる通達等では処理しきれない。保険商品を後追いする形で税務取り扱いが改定されてきた歴史がそれを物語っている。今回の問題の対応を含め、今後も、この変更可能性については考慮しておく必要がある。イタチごっこはまだまだ続くように思える。








