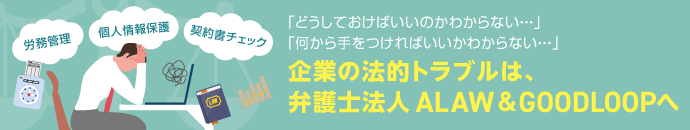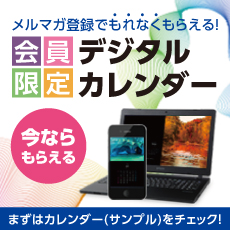会食に参加している時間は「労働時間」にあたるのか?

「企業側」の労務問題を取り扱っている弁護士植木博路です。
今回は、「会食に参加している時間は『労働時間』にあたるのか?」を考えたいと思います。
なお、本コラムは、WEBサイト、「企業側の労務」に掲載した内容を、一部加筆修正したものです。
まず、会食に参加している時間は「労働時間」にあたるのかを考えるにあたっては、「労働時間」とは何かを明らかにする必要がありますが、この点については、上記WEBサイト掲載のコラム(「労働時間」とは、「労働時間」とは②)をご覧ください。
1 原則、労働時間には該当しない
労働者が、取引先との会食に、上司から誘われて、断り切れずに参加したような場合です。会食は、本来の業務ではありません。会食が今後の営業に有利に働くなどの事情があったとしても、また、仮に上司の指示があったとしても、労働時間には該当しないと考えます。
なお、上司が会食への参加を指示した場合には、そのような指示が有効か否かが問題となりますし、また、そのような指示は具体的内容如何ではパワーハラスメントになる可能性があります。
2 労働時間にあたる場合
ただし、例外的に、労働時間にあたる場合はあります。
次の裁判例があります。高松高判令和2年4月9日(令和元年(行コ)第20号)です。
裁判所は次のように述べました。
「・・・業務に伴う懇親会等は、通常は、業務終了後の会食ないし慰労の場であることからすれば、懇親会等への出席は、基本的には使用者の指揮命令下に置かれたものとはいい難く、社会通念上、当該懇親会等が業務の遂行上必要なものと客観的に認められ、かつ、それへの出席や参加が事実上強制されているような場合にのみ使用者の指揮監督下に置かれたものと評価でき、その参加に要した時間は労働時間に当たると解するべきである。
以下、個別の労働時間として争いのある懇親会等について、労働時間に当たるか否かについて検討する。
ア 5月27日
前記認定のとり、東京の本社からD1などの顧客挨拶のために統括部長代理ら3名が高松に来ていたことから、E1部長が主催者となり、同3名との懇親会を企画し、C1はこれに出席した。
上記懇親会への直接的な参加強制はなかったものの、C1の直属の上司が主催者であり、四国エネルギー営業部の所属員のほとんどが参加するものではあったから、情報部門のリーダーの立場にあったC1としては、欠席することは事実上困難であったと考えられること(そのため、同日はフラダンスの練習の予定があったが、それを取りやめて、上記懇親会に参加している。)、慰労、懇親の趣旨も含まれるものであったとしても、本社の幹部社員との業務に関する意見交換の意味合いも否定できず、業務の円滑な遂行上も必要であったと認められるから、午後6時から午後9時までの上記懇親会参加時間3時間は労働時間と認めるのが相当である。
イ 7月3日
上記懇親会への参加については、業務性があるとして、午後6時から午後9時までの間が労働時間に該当することについて当事者間に争いがない。
控訴人は、C1の友人宛ての「今日は出張者と飲みやった」とのメールの送信時刻である午後10時6分を終業時刻とすべき旨主張するが、懇親会終了後直ちに上記メールを送信したとは限らないから、メールの送信時刻が懇親会終了時刻であるということはできず、その他、終業時刻(懇親会終了時刻)が午後9時よりも後であることを認めるに足りる的確な証拠はない。
ウ 7月4日
前記認定のとおり、前任の四国支店長が東京から高松に出張に来る予定であったことから、総務部長及び社会ネットワーク部長によって懇親会が企画されたものであり、上記懇親会の参加者は明らかではないが、C1が友人に宛てたメールに、「呼ばれてて」、「他に呼ぶ人探しといて」と記載していることや部長職の主催であったことからして、情報部門のリーダーの立場にあったC1としては欠席することは事実上困難であったと考えられること、慰労、懇親の趣旨も含まれるものであったとしても、幹部社員との業務に関する意見交換の意味合いも否定できず、業務の円滑な遂行上も必要であったと認められるから、一般的な懇親会参加時間3時間(18時~21時)の限度で、労働時間と認めるのが相当である。上記懇親会が上記時間以上要したことを認めるに足りる的確な証拠はない(C1の22時28分の「おつきあい終了!つかれたぁ」とのメールのみで、同時刻まで懇親会がされたとは認められない。)。
エ 8月20日
四国エネルギー営業部の送別会が開催され、東京出張から戻ったC1は、これに参加した。同送別会の参加者は明らかではない。
送別会は、一般的に、異動者への慰労や激励の趣旨が強く、業務の遂行上必要なものとはいえない。また、同送別会の参加者は明らかではなく、参加が事実上強制されていたと認めるに足りる証拠はない。
したがって、上記送別会に参加した時間を労働時間であると認めることはできない。
オ 9月25日
前記認定のとおり、上記懇親会は、SE部門を中心とする懇親会で、C1の所属する四国エネルギー営業部は参加しないかと声が掛かった程度であって、事実上参加を強制されたとは認めるに足りる的確な証拠はない。また、C1がSE部門との関わりが多くなかったことからしても、同懇親会への参加が業務の遂行上必要であったとも認められない。
したがって、上記懇親会への参加に要した時間を労働時間と認めることはできない。
カ 10月24日
前記認定のとおり、C1は、午後6時30分からのD1配電部との懇親会に参加しており、当時、C1の主な営業先はD1情報通信システム部門であり、配電部との関わりは間接的なものにとどまっていたものの、C1は、平成26年度において、情報部門のリーダーとして、配電部に対する営業も担当の範囲内であり、同部とも依然として仕事上の付合いがあったことからすると、上記懇親会は、今後の円滑な取引継続を期待した取引先に対する接待であると認められ、上記懇親会の参加時間のうち一般的な懇親会の時間である3時間の限度で労働時間と認めるのが相当である。それ以上の時間を要したことを認めるに足りる的確な証拠はない。
キ 10月27日
前記認定のとおり、C1と総務部の社員がSPに昇格したことから、L1四国支社長と総務部長の企画によりC1らの昇格を祝う目的で開催された懇親会である。
昇格を祝う懇親会は、一般的に昇格者に対する慰労や激励の趣旨が強く、業務の遂行上必要なものとはいえない。
したがって、上記懇親会への参加に要した時間を労働時間と認めることはできない。
ク 11月12日
前記認定のとおり、上記は、C1の直属の部下であるG1が東北地方に短期出張することとなったことから、四国エネルギー営業部において開催された同人の壮行会である。
壮行会は、一般的に、激励の趣旨が強く、業務の遂行上必要なものとはいえない。
したがって、上記壮行会に参加した時間を労働時間であると認めることはできない。
3 コメント
労働者が会食に参加している時間は、労働時間ではないと考えてよいと思います。ただし、例外的に、社会通念上、会食が業務の遂行上必要なものと客観的に認められ、かつ、それへの出席や参加が事実上強制されているような場合には労働時間に当たるとされますので、注意が必要です。会食への参加が強制とならないように注意する必要があります。
また、会食への参加時間を労働時間として扱うこととし、この参加時間につき一定の手当を支給するという対応も考えられます。この場合、会食参加は、通常の業務に比べれば、労働密度は小さく、労働者側の負担も小さいため、通常の業務時間に対する賃金よりも、低額の賃金を支払うという扱いには合理性があると考えます。ただし、このような取扱いには労働者との合意や賃金規程の変更等が必要となる可能性がありますので、注意が必要です。