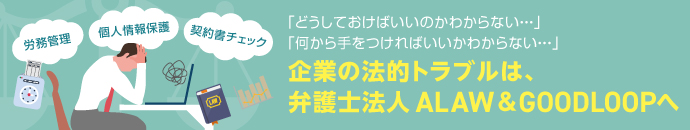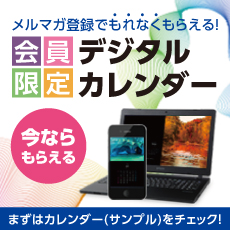ハンコの効用

稟議書の決裁印であったり,回覧板の認印であったり,私たちの周りには「ハンコ」があふれています。この「ハンコ」には,法律的にどのような意味があるのでしょうか。
契約書を見てみましょう。ほとんどの契約書では,会社であれば会社の社判が,個人であれば個人の印が押されています。これらのハンコがなかったら,どうなるでしょうか。無効となるのでしょうか。
実はハンコがなかったとしても,契約が無効となるものではありません。契約は口頭でなされても有効です(保証契約など例外はあります。)。お互いの合意があれば契約自体は有効に成立するからです。契約書は,まさに,そうした合意があったことを証するものですし,そこに押されるハンコも,署名とともに,書かれた内容を確認して押されるものです。したがって,契約を有効とするために必須の要素ではありません。
遺言書など例外はありますが,これは他の文書についても言えることです。
では,どうして,私たちはハンコを押すのでしょうか。
一つは習慣です。同僚に渡す伝言メモに記名がわりにハンコを押すとか,自前の書籍に所蔵印を押すなど,さほど意味はなくても便利にハンコを使う場面は多々あります。
しかし,今一つ重要な理由があります。それは,文書が偽造されたものではないこと,言い換えれば,確実にその人の意思に基づいて作られたものであることを示すという目的です。
たとえば,すべてがワープロ打ちされた契約書を想定します。仮にハンコが押されていない場合,後々,「こんな契約書は交わしていない」「偽造されたものだ」と争われたときに,反論する材料は契約書の中には見当たりません。しかし,契約書に実印での押印があったら,どうでしょうか。印影(ハンコの押された跡)から,その実印の持ち主が押印したことが強く推測され(通常,ハンコを押すことができるのは,そのハンコを慎重に保管している持ち主に限られるからです。実印では特にそう言えます。),さらに押印の事実から,その人物の意思に基づいて文書が作成されたことが強く推測されます(作成意思がない文書に,敢えて作成者として印を押す事態はあまり想定されないからです。)。こうして,疑義を晴らすことができるのです。民事裁判でも,こうした考えをもとに「二段の推定」と呼ばれる推定がなされます。
このように,「必須ではないが証拠上重要となりうる」というのが,大方のハンコの法的性質です(繰り返しますが,押印がないと無効となる文書も存在します。)。そして,ここまで簡易的に「ハンコ」と呼んできましたが,法律では「印章」「印影」「印鑑」など文脈により言葉が使い分けられています。デジタル化のなかで,今一度ハンコの意味や役割を掘り下げて考察するのも一興です。