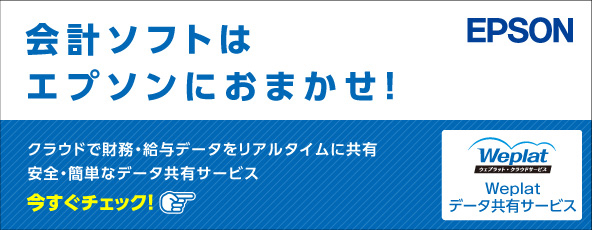破産会社も前期損益修正と異なる取扱いは許容されないと判断
消費者金融業を営んでいた破産会社の過払金返還請求権に係る破産債権が破産手続において事後的に確定した場合、その請求権の発生原因となった制限超過利息等に係る受領金額を受領した各事業年度に遡って益金の額から減額して計算すべきか否か、つまり前期損益修正と異なる取扱いが許容されるか否かの判断が争われた事件で最高裁(深山卓也裁判長)は、破産会社側の請求を認容した高裁の判断には法令違反があるとして破棄する一方、一審の判断は正当であるから破産会社側の控訴を棄却する判決を言い渡した。
この事件は、消費者金融業等を営んでいた破産会社の破産管財人が、各事業年度において支払いを受けた制限超過利息等に対する不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続において確定したことによって、これに対応する各事業年度の益金の額を減額して計算すると納付すべき法人税の額が過大になったとして、各事業年度の法人税について更正の請求をしたもの。
ところが、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分をしてきたため、主位的には各通知処分の一部取消しを、予備的には制限超過利息等に対応する法人税相当額の一部についての不当利得返還等を求めて提訴したのが発端となった。
一審は破産会社側の請求を棄却したが、控訴審は、企業会計原則は企業の経済的活動が半永久的に営まれるとの仮定が成り立つことを前提とする考え方に基づくものであるが、破産会社は破産手続による清算の目的の範囲内において破産手続が終了するまで存続するにすぎないからその考え方は妥当せず、会社法上の前期損益修正に係る規定の適用もないと解すべきであると指摘。
過払金返還請求権に係る破産債権のうち既に配当がされた部分に対応する制限超過利息等に加え、まだ配当がされていない部分に対応する制限超過利息等についてもこれらを受領した日の属する事業年度に遡って益金の額を減額計算することは公正処理基準に従った計算方法に合致すると判示して、破産会社側に軍配を上げた。しかし、控訴審の判断を不服とした国側が上告、最高裁でその判断が争われてきたという事案である。
最高裁はまず、法人税法等には法人が受領した制限超過利息等を益金に算入して申告した後の事業年度にその制限超過利息等についての不当利得返還請求権に係る破産債権が破産手続により確定した場合に、前期損益修正と異なる取扱いを許容する特別の規定はなく、企業会計上もそうした場合に過年度の収益を減額させる計算をすることが公正妥当な会計慣行として確立していることはうかがわれないことからすると、法人税法がそうした原則に対する例外を許容しているものと解することはできないし、不当利得返還請求権に係る破産債権の一部ないし全部について現に配当がされ、その法人が現に遡って決算を修正する処理をしたとしても異なるものではないと指摘。
そうすると、制限超過利息等の受領の日が属する事業年度の益金の額を減額する計算をすることは公正処理基準に従ったものということはできないと解するのが相当と判示した。結局、控訴審の判断には法令違反があるから破棄すべきであり、一審判断は正当であるから破産会社側の控訴は棄却すべきであるという国側逆転勝訴の判決を言い渡した。
(2020.07.02最高裁第一小法廷判決、平成31年(行ヒ)第61号)
提供元:21C・TFフォーラム(株式会社タックス・コム)