| 5-I-4 |
| I 棚卸資産の評価 |
| 4 原価差額の調整 (1)原価差額の意義 標準原価計算制度のほか実際原価計算制度を採用している場合でも、計算の便宜性などから、たとえば製造間接費の配賦を予定率で行うような場合に、税務上の取得価額(実際に要した原材料費・労務費・経費の合計額)と法人の計算する取得価額との間に差異が生ずることがあります。 この差異を「原価差異」と呼び、会計上は次のように処理すべきものとされています。
以上の会計上の取扱いに対して税務上は、法人の算定した製造原価が実際原価と異なる場合、それが適正な原価計算に基づいて算定されていれば、原則としてその原価を取得価額とみます(令32 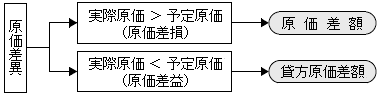 原価差異は、法人計算による原価が実際原価に満たない場合の「原価差損」(借方原価差額)と、超える場合の「原価差益」(貸方原価差額)に分けられますが、税務上は原価差損のみを「原価差額」といい、原価差益のことを「貸方原価差額」と呼んでいます。そして、上述(2)でいう多額の原価差異が生ずる場合の調整計算は、原価差額(借方原価差額)についてのみ要求されます(基通5−3−1)。 原価差額が多額か否かは、具体的にその額が総製造費用の『1%』を超えるかどうかで判定します(基通5−3−3)。したがって、総製造費用のおおむね1%相当額以内であれば、原価差額の全額をその事業年度の損金に算入することができます。 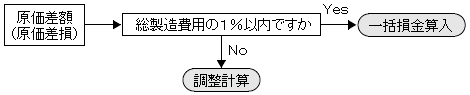 1%以内かどうかは事業の種類ごとに判定しますが、法人が製品の種類ごとに原価計算を行っているときは、継続して製品の種類ごとに判定することができます(基通5−3−3(注))。さらに、各製品ごとの原価差額が1%相当額を超える場合でも、工場ごとに原価差額を調整し、工場ごとの各製品の原価差額が総製造費用の1%相当額以内であれば、やはり調整を要しません(基通5−3−4)。 なお、原価差額の調整を省略するときは、総製造費用の1%以内である旨の計算を明らかにした明細書を、確定申告書に添付しなければなりません。 (2)原価差額の調整方法 原価差額の調整方法としては、一工場から他工場へ、また、仕掛品から半製品、半製品から製品への段階的な調整方法(「ころがし調整」)が考えられますが、計算の簡素化等の観点から、「簡便調整」が認められています。つまり、原価差額を仕掛品、半製品、製品の順にころがして調整せず、その原価差額を一括して、次の算式で計算した金額を期末棚卸資産に配賦することができます(基通5−3−5)。
なお、原価差額を個々の棚卸資産に配賦しないで一括して資産計上することも認められます。その場合、一括処理した金額がそのまま翌期の損金に算入されます(基通5−3−7)。 原材料の受入れについて見積原価等を採用している場合に生ずる「原材料受入差額」は、他の原価差額と扱いを変えて当期の原材料払出高と期末原材料棚卸高に配賦します(基通5−3−8)。その際には、当期原材料払出高に対応する原価差額に関し、当期に上記の簡便調整計算を適用することができます。 なお、原材料受入差額のうち期末原材料棚卸高に対応する部分の金額は、翌期の製造原価に含められます(基通5−3−8(注))。
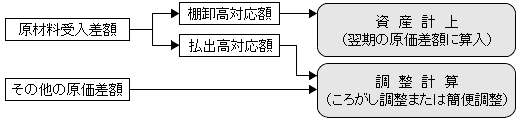 |