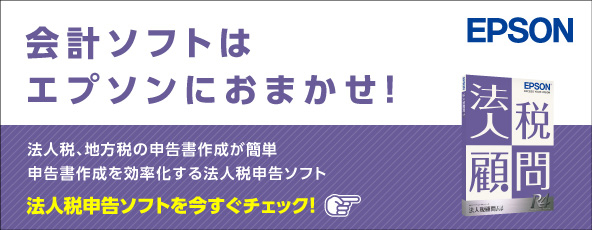フリンジ・ベネフィット~お国柄色々 前編

フリンジ・ベネフィット~お国柄色々(1)
(1) 使用者から受ける現金以外の様々な形での給付
給与所得者は、使用者から現金以外の様々な形で給付を受けることがある。例えば、・金銭形態のもの(災害・疾病に対する見舞金、社内金融)、・現物形態のもの(食事,社宅,保養施設)、・社会保障(年金,保険)といった色々な形態がある。これらを総称して「フリンジ・ベネフィット」と呼ぶ。
戦後の焼跡からの復興の過程で、労働組合等はこれらの項目を労働協約の中に含めることにより、労働条件・福祉水準の改善を図り、生活文化の向上を図ってきたと言えるであろう。また企業側でも、住宅や福利厚生施設を設けて、その利用を広く従業員に供することにより、結果として我が国の福祉社会の建設は産業界の貢献なくしてはあり得ず、国のやるべき仕事を世の企業が肩代わりしてきたと言われるほどである。
筆者は、繊維会社の大きな地方工場(女工さんが2000人以上いた)の「社宅」で育ったが、昭和30年代のそこでは「夏休みの海水浴」、「秋の運動会」(工場内のグラウンドで開催)、「年末のクリスマス・パーティー」は全て工場主催であり、四季折々には「名画鑑賞会」(工場内に映画館もあった)、そしてなんと「春祭り」すら、工場所有の神輿を繰り出し、子供も大人も工場支給のハッピを着て行われていたものである。日本の高度成長真っ只中の、なつかしい一つの典型的な景色であったのだろう。
(2) 我が国では所基通においてキメ細かく課税除外措置を規定
ところで、現在世界の主流となっている「包括的所得概念」の下では、これらフリンジ・ベネフィットの給付のほとんど全てが、理論的には給与所得者の「所得」を構成することに異論はないであろう。すなわち、一時的・偶発的・恩恵的な利得であっても、利得者の担税力を増加させるものである限り、課税の対象とするとの考え方であるからである。
しかしながらこの分野に関しては、原理・原則通りにものごとを進めてはギスギスしてしまうため、何らかの課税除外が行われるのが、広く世界共通の傾向である。我が国においては、所得税基本通達において実にキメ細かく課税除外措置を規定している。例えばレクレーション費用を使用者が負担したケースについては、「社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会」については、役員だけに費用を負担するケースや、不参加者に金銭を支給するケースを除き、「課税しなくて差し支えない」とされている。
(3) 課税除外措置が全く存在しない国もある
ところが米国においては、こうしたレクレーション費用に係る課税除外措置は、全く存在しないようである。制度上、全て給与所得として課税されることになるのである。そもそも会社内でレクレーションを行う習慣に乏しく、「やるなら税金を払った上でやってくれ」という割り切りのようである。
また、イギリスにおいても、レクレーション費用については、ただ一つの除外措置を除いて課税される。そのただ一つの例外は、「クリスマス・パーティー」である。クリスマスだけが、「唯一、正しく好ましいと誰もが認める行事」という訳のようだ。一方、ドイツでは「社内行事、例えば従業員慰安旅行、クリスマス・パーティー、記念祝典などを実施した場合、それが通常の社内行事であり、かつ通常要する費用の範囲を超えない限り、課税されない」とされ、なんとなく我が国と親近感があるのである。
フリンジ・ベネフィット~お国柄色々(2)
(1) 通勤費の非課税規定が設けられていないイギリス
多くのサラリーマンは、会社から通勤手当を支給され、それが「非課税」扱いになっていて、何の疑問も感じていないことだろう。もらった手当はそのままJR等の定期券の購入にあてられ、手元には1円も残らないからである。
ところがイギリスに行くとそうはいかないようで、通勤費は家事費の範囲に属し、特段の非課税措置は設けられていない。その“こころ”は、「会社の近くに住もうと思えば住めるのに、わざわざ遠くの郊外に住むのは個人的な好みのゆえだから、税制上配慮する必要性は薄い」というもののようである。なるほど、森に近いからとか、広い庭を持ちたいからとかの個人的嗜好で郊外を選ぶというのなら、さもありなんと思われる。
しかしイギリスを旅行してみると、ロンドン市内などに家を買うことは難しいため、相当遠くの郊外からラッシュの電車を乗り継いで通勤(痛勤?)している人たちも多いと見受けられるのである。このような通勤事情の変化に応じて税制も変わるべきと思われるのに、いっこうに制度改正しようとしないのは、伝統を重んじるイギリスの頑固さだろうか。そろそろ日本を見習ったらどうですか? と言いたい気がするのである。
(2) 時代に合わせて対応している通勤費の非課税限度額
ところで、1月あたり10万円までという我が国でつい最近まで続いていた非課税の基準は、平成10年の税制改正で、「東京までおおむね100キロメートル程度の通勤圏」として、新幹線通勤の東京.三島、東京・宇都宮、東京・高崎間の1ヵ月分の定期乗車券代を考慮したものとのことである。
しかし最近の電車広告を眺めると、住宅地として上毛高原や喜連川などの売り出しが目に付くところ、上毛高原は定期代が1ヵ月12万円を超えるし、喜連川も11万円を超えている。そろそろ基準が合わなくなって来ているな、と思っていたところ、平成28年度の税制改正で限度額が15万円に引上げとなった。時代に合わせて税務当局も迅速に対応しているようである。
ところで、今日的な問題として、今後リニア・モーターカーの運行が開始したら、どうなるのだろうか。東京・名古屋をわずか40分で結ぶわけなので、名古屋から東京(あるいは東京から名古屋)に通勤するビジネスマンの出現は必至と思われる。
(3) 非課税として扱う理論的根拠としての「実費弁償論」
ところで、フリンジ・ベネフィットを非課税として扱う理論的根拠として、「実費弁償論」がある。通勤定期代を収入金額に含めたとしても、それは職業上の必要に供されるもので、収入と同時に必要経費にあてられたものと見るべきだから、原則として所得の発生は認められない、という考え方である。このような理論があてはまる通勤費は、同じフリンジ・ベネフィットといってもレクレーション費などとは性質を異にすると言えよう。
名古屋から東京にリニア通勤して通勤費を支給されるビジネスマンに、「担税力」を増す何ほどかのベネフィットが発生しているかと考えると、「俺は他の社員よりきわだって遠方からの通勤を、会社から期待されている」といった何ほどかの心理的優越感と、東海道を眺望しながらの通勤という満足感が考えられるかもしれない。
しかし一方で、遠距離通勤を強いられる肉体的負担や不便さ(自宅に忘れ物をしたケースや、悪天候で列車が止まってしまったケースを考えてみよ)を考慮すれば、それほど担税力が増すとは考えにくいのである。金額基準の扱いは悩ましいものであるが、実費弁償である限り、金額基準を撤廃して全額非課税扱いする選択肢もあるのではないか、と思う。
後編へ続く