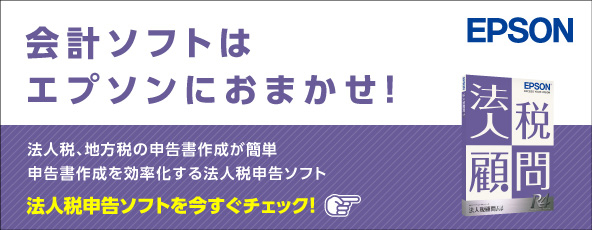シリーズ「法人税・グレーゾーンの税法解釈」(後編)

<シリーズのはじめに当たって>
租税法の基本原則の一つに「課税要件明確主義」という原則がある。
課税要件明確主義とは、課税要件についての定めはなるべく一義的で明確でなければならないという原則である。租税法規が一義的で明確でないときには、納税者は自らの行動の結果として生じる税負担を予測できなくなってしまう。また、租税の執行において行政に判断の幅を与えてしまい、実質的に課税・非課税の判断が課税当局の匙加減ひとつで左右され、憲法が規定する租税法律主義の原則が空文化してしまうことにつながるからであると説明されている。
しかしである。あらゆる経済事象や経済取引をあらかじめ想定してそれぞれの具体的事実に即して課税要件を個別に法令上これを定めることは、およそ不可能な事柄ともいえる。また、画一的・機械的な規定がかえって実情に応じた課税の妨げになり杓子定規な課税が横行することも考えられる。このため、租税法令や国税庁通達では課税要件に関し、例えば「不相当に高額」「著しい低下」「通常要する費用」「おおむね」「社会通念上一般的に」などという、一定の幅を持つ抽象的な概念で規定しているケースが見受けられる。
また、言葉の意味自体は明確だがその内容において解釈の余地が大きいな規定も少なくない。例えば「交際費」、「修繕費」そして「寄附金」などについては、言葉の意味としては明確と言えるが、類似費用や隣接費用との境目が明確でない、いわゆる税務上のグレーゾーンと言われる領域が多数存在している。
これらのグレーゾーンの存在は、実務家をおおいに悩ましている。本シリーズではこれらの税務上のグレーゾーンと言われる個々の規定ごとにその解釈基準や判例等などを取り上げ参考に供する。
前編からの続き
3 グレーゾーンに判断に関する判例・裁決
上記の租税特別措置法上の規定は「これらに類する行為のために支出するもの」も含むなど交際費の範囲をかなり広く規定している。このため隣接費用との境界を巡るグレーゾーンも相当広くなっており、納税者側と課税庁の間において解釈が対立する例も多い。以下、これらのグレーゾーンの解釈の指針になるとも思われるいくつかの裁判例や裁決事例を紹介し参考に供する。
① 福利厚生のための支出が交際費から除外されたことの趣旨が示された事例(昭51.7.28東京高判56)
「もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」を特に交際費から除外しているのは、この種の費用が、従業員個々の人の業務実績とは無関係に従業員全体の福利厚生のために支出されるものであり、法人おいて負担するのが相当な費用であるので、通常要する範囲を超えない限り全額損金算入を認めても、法人の社会的冗費抑制の目的に反しないとしたためであると解される。
② 福利厚生のための「通常要する費用」の判断基準が判示された事例(昭57.8.31東京地判55)
福利厚生費が交際費から除外されるためには、もっぱら従業員の慰安のための行事の費用であると同時に、当該行事が法人が費用を負担して行う福利厚生事業として社会通念上一般的に行われていると認められるものであることを要すると解するのが相当であり、たとえ従業員の慰安のための行事であっても、通常一般的に行われている程度を超えるときは、その費用は通常要する費用の範囲を超えるものとして交際費等に該当するものと解すべきである。
そうして、当該行事が右の通常一般的に行われる範囲内のものであるか否かは、当該行事の規模、開催場所、参加者の構成及び1人当たりの費用額、飲食の内容等を総合して判断すべきである。
③ 1人当たり2万9千円程度の日帰り旅行費用は交際費等には該当しないと判断された事例(平29.4.25福岡地判27)
「感謝の集い」と名付けられた本件行事は、原告及び協力会社等の従業員全員を対象とし、原告代表者が従業員に対する感謝の意を表し、従業員の労働意欲を向上させるために、他の従業員との歓談や交流の機会、コース料理及びコンサート鑑賞の機会を提供するものである。したがって、本件行事は「専ら従業員の慰安のために行われる」ものといえる。
そして、本件行事の日程、特に、従業員の移動時間及び本件ホテル行事の会場の性質(従業員がふだん訪れることのない大型リゾートホテルの宴会場であること)並びに本件ホテル行事の内容(全従業員同士が集まる唯一の機会であり、従業員が普段味わう機会のないコース料理やライブコンサートの鑑賞を内容とするものであること)に照らせば、本件行事は、従業員にとってある程度の非日常性を有する場所への移動の要素を含むとともに、また、全従業員が一堂に会し、特別のコース料理を共に味わい、ライブコンサートを楽しむという非日常的な内容を含むものであって、従業員全員を対象とする「日帰り慰安旅行」であったといえる。
さらに、本件行事に係る参加者一人当たりの費用は2万1972円ないし2万8726円であるところ、本件行事の会場及び内容等とともに、本件行事は、年1回、従業員の移動時間を含めると約8時間から11時間を掛けて行われる行事であることに照らせば、通常要する費用額を超えるものとは認め難い。
④ 販売促進のための支出が交際費等に当たらないと判断された事例(平4.1.22大阪地判63)
製造業者が、自社製品を購入してもらったことへの謝礼等の趣旨で、得意先を観光旅行に招待した場合には、そのために要する費用は交際費に該当し、当該事業年度の損金の額に算入することは認められないが、他方、自社製品の商品知識の普及等を目的として、得意先に工場の見学をさせる場合には、このような行為は、得意先に対する接待、供応というよりも、販売促進のために必要な行為というべきであるから、それに通常要する費用の額は、販売促進費として、損金の額に算入することが許されると解される。
⑤ 交際費から除外される会議費の判断基準が示された事例(平4.11.25神戸地判)
「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を提供するために通常要する費用」というのは、冗費濫費のおそれがないような、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常提供される飲食程度を越えない飲食物等の接待に要する費用のことであると解すべきであり、このようなものである限り、その全額が交際費等から除外される。
このことは、会議が社外の会場を借りて行われた場合であっても同様であるが、いずれにしても、支出の前提になる会合が会議の実態を備えたものでなければならないものであり、会議が単なる名目、形式にすぎず、会議としての実体を備えているということができない場合は、その費用を交際費等の範囲から除外することができない。そして、会議が実体を備えているかどうかは、開催場所、会議の議題及び内容並びに支出内容等を総合的に検討して判断すべきである。
⑥ 開店祝いの花輪代は広告宣伝費ではなく交際費等に当たると判断された事例(平7.10.13静岡地判4)
冷凍設備工事業を営む原告会社が取引先店舗の開店祝いに贈呈した花輪代は、特段の事情が無い限り、工事発注に対する謝意と今後の好誼を願う意図を込めたものであり、取引先店舗との取引関係の円滑な進行を図る目的のためのものであるから、広告宣伝費ではなく、交際費等に当たる。
⑦ 談合金の支払は交際費等に当たると判断された事例(平15.12.24那覇地判14)
外注費の名目で支出された金員が防音工事の入札参加者の間における一種の談合にも類する事実関係に基因した金員の支払と評価される。その金員は事業に関係ある者に対する贈答に類する行為のために支出された費用として、交際費に該当する。
⑧ 遊園施設への優待入場券に係る費用が交際費等に該当するものと判断された事例(平21.7.31東京地判19)
原告が本件優待入場券を発行してこれを使用させたことについては、原告の遂行する事業に関係のある企業及びマスコミ関係者等の特定の者に対し、その歓心を買って関係を良好なものとし原告の事業を円滑に遂行すべく、接待又は供応の趣旨でされたと認めるのが相当であり、これを使用して入場等をした者に対して役務を提供するに当たり原告が支出した上記の費用については、上記のような支出の相手方、支出の目的及び支出に係る行為の形態に照らし、交際費等に当たると認めるのが相当である。
⑨ 商品販売に係るコミッションは交際費等に該当しないと判断された事例(平3.7.10国税不服審判所裁決)
請求人と得意先の代表者等との間におけるコミッション及びロイヤリティ契約は、得意先の代表者等が所有するブランド商品の販売に係るコミッションないしロイヤリティの支払に関して、請求人と得意先の代表者等との間で正当に取り交わされたものであると認められるから、この契約等に基づき、請求人が当該ブランド名を使用して商品販売を行ったことによりそのコミッションないしロイヤリティとして支払った手数料及び販売した商品のクレーム費用は、交際費等には該当しない。