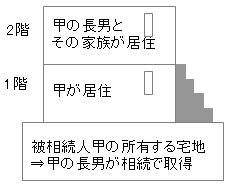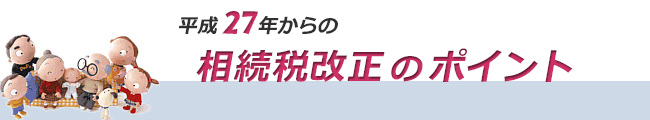
| [前へ] | [メニューへ] | [次へ] |
(4)小規模宅地特例の見直し
 小規模宅地特例とは、被相続人等の「居住の用に供していた宅地等(特例居住用宅地等)」、「事業の用に供していた宅地等(特定事業用宅地等)」、「貸家の敷地など貸付の用に供していた宅地等(貸付事業用宅地等)」等を、その親族が相続等により取得する場合、一定の要件の下で、これらの宅地等の相続税対象額を相続税の課税対象から減額できる制度をいいます。
小規模宅地特例とは、被相続人等の「居住の用に供していた宅地等(特例居住用宅地等)」、「事業の用に供していた宅地等(特定事業用宅地等)」、「貸家の敷地など貸付の用に供していた宅地等(貸付事業用宅地等)」等を、その親族が相続等により取得する場合、一定の要件の下で、これらの宅地等の相続税対象額を相続税の課税対象から減額できる制度をいいます。<1>特定居住用宅地等に係る特例の見直し
小規模宅地特例については、平成27年以降の相続税改正に先駆けて、平成26年1月1日以後の相続等により取得した特定居住用宅地等につき、次の見直しが行われています。
1)二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地特例
イ.被相続人の居住用の宅地等の範囲
被相続人の居住の用に供されていた宅地等を相続等により取得した被相続人の親族が、原則として相続開始時にその宅地等の上に存する被相続人の居住用家屋に同居していた者であって、相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月経過日)まで引続きその宅地等を有し、かつ、その家屋に居住している場合は、その宅地等は特定居住用宅地等に該当し、相続税の課税価格の計算上、その宅地等のうち240平方メートル(平成27年以降の相続等により取得した宅地等は330平方メートル。後述3)参照。)までの評価額の80%相当額が減額されます(租税特別措置法(措法)第69条の4第1項、第3項第2号イ)。
ロ.二世帯住宅の敷地における「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」の範囲
地価が高く住宅事情の厳しい都市部では、親の土地の上に二世帯住宅を建て、別生計の親子が住む場合があります。最近の二世帯住宅は、プライバシー尊重のため、一棟の家屋でも親子の居住スペースを独立させ、内部では互いのスペースへの行き来ができないものが増えています。例えば1階と2階が分離され、内部で行き来ができない二世帯住宅で、親子が1階と2階に分かれて居住していた場合に、親の死亡により子がその住宅の敷地を相続により取得し、前述イの特定居住用宅地等に係る小規模宅地特例の適用を受けようとするときは、その子が「被相続人の居住の用に供していた宅地(被相続人の自宅の敷地)等を相続等」し、かつ、「相続開始時に被相続人の居住用家屋に同居していた者」に該当するかどうかが問題となります。
平成25年度税制改正前の取扱いでは、各世帯の居住スペースが区分され、構造上内部で行き来が不可能な二世帯住宅の場合、それぞれの区分ごとに独立した家屋と考えられることから、その住宅に居住する二世帯は同居していないものとされていました。このため、被相続人の居住スペース以外の部分(被相続人の子の居住スペース)に対応する宅地等については、原則として被相続人の居住の用に供していた宅地等に該当しないものとされ、特定居住用宅地等に係る小規模宅地特例の適用が認められていませんでした。
これが平成25年度税制改正により、特定居住用宅地等の前提となる「被相続人の居住の用に供されていた宅地等」の範囲について、被相続人とその親族(子)が一棟の建物のなかで居住していたときは、その建物の構造にかかわらず、その親族が居住の用に供していた部分の敷地に対応する部分も、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に含まれることとされました。
ただし、上記の一棟の建物が「『建物の区分所有等に関する法律』第1条の規定に該当する建物(原則、区分所有建物である旨の登記がされている建物をいう。以下、「区分所有建物」という。)に該当する場合には、建物の敷地のうち被相続人が居住の用に供していた部分に対応する部分のみが、被相続人の居住用の宅地等とされる(租税特別措置法施行令(措令)第40条の2第4項、措法通達69の4-7(注))ので、注意が必要です。
ハ.被相続人の親族の同居要件
前述イの「被相続人の居住用家屋に同居していた者」の要件(以下「同居要件」という。)に該当する者とは、被相続人の親族のうち、「相続開始の直前において、その宅地等の上の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物のうち、『一定の部分』に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その建物に居住している」ものをいいます(措法第69条の4第3項第2号イ)。
この場合の『一定の部分』とは、次のⅰ又はⅱに掲げる区分に応じ、それぞれに定める部分となります(措令第40条の2第10項)。
| ⅰ. | 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が、区分所有建物である場合には、当該被相続人の居住の用に供されていた部分が該当します。 二世帯住宅が親(被相続人)と子により区分所有されていた場合は、相続開始直前において、その建物のうち親が居住していた部分に子が居住しなければ、「同居要件」を満たすことができないことになります。 |
| ii. | ⅰ.以外の場合は、被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分が該当します。 |
ニ.事例による区分所有の登記がされた二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地特例の適用の検討
被相続人が所有する宅地の上に被相続人(甲)と別生計の長男が二世帯住宅である一棟の建物を所有し、1階は被相続人のみが居住し、2階は被相続人の長男夫婦が居住していた場合に、長男がその宅地を相続したとします。この場合、その一棟の建物につき被相続人が1階、長男が2階の専有部分につき区分所有権を登記しているときは、前述ロ.より、長男が相続した宅地等のうち、被相続人が居住の用に供していた1階に対応する部分のみが被相続人の居住用の宅地等とされます。この場合、長男はその建物の1階に居住していなかったことから、前述ハⅰ.の同居要件を満たすことができず、よって特定居住用宅地等に係る小規模宅地特例の適用を受けることはできません。
なお、本事例においてその二世帯住宅である一棟の建物が親もしくは子の単独所有又は親と子の共有である場合は、前述のロ及びハⅱより二世帯住宅の敷地全体が特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地特例の適用を受けることができます。二世帯住宅については区分所有の登記の有無により、小規模宅地特例の適用の可否が分かれることになるので、注意が必要です。
二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地特例
|
| [前へ] | [メニューへ] | [次へ] |