| 1.1.2 |
| 1.1.2 課税における宗教活動、公益事業、収益事業の区分の意味 |
宗教法人法は、宗教法人の活動や事業を、(1)「宗教活動」、(2)「公益事業」、(3)「収益事業」の3つに区分して取り扱っています。これにしたがい、宗教法人会計は、(1)宗教活動会計、(2)公益事業会計、(3)収益事業会計の3つに区分されています。法人税法上、宗教法人の「非収益事業」は非課税とされています。言い換えると、「収益事業」だけに課税されます。ただ、宗教法人法に従って作成される宗教法人会計における収益事業と税法上の収益事業とは、必ずしも内容が一致しません。課税庁は、「対価 対 寄附(喜捨)基準」のような概括基準や税務通達を活用して「宗教活動」に対する課税権の行使を積極化、収益事業課税の範囲を広げようとする傾向にあります。 |
| ◎収益事業課税における宗教法人法と税法の立ち位置 宗教法人は、「宗教的側面」ないし「聖」の面と、「世俗的側面」ないし「俗」の面をあわせ持った法人です。宗教法人法は、宗教法人の活動や事業を、(1)「宗教活動」、(2)「公益事業」、(3)「収益事業」の3つに区分して取り扱っています(宗法2、6 一般に、(1)と(2)を「非収益事業」、(3)を「収益事業」といいます。一方、宗教活動に加え幼稚園など公益事業を行っている場合には、当該公益事業を含めて「本来の事業」といいます。 ここで、宗教法人に最も関係の深い税金の一つである法人税を例に、これらの活動/事業に対する課税取扱いについてみてみます。 法人税法は、宗教法人の「非収益事業」を非課税としています。言い換えると、「収益事業」には課税されます。ただ、宗教法人法に従って作成される宗教法人会計における収益事業と税法上の収益事業とは、必ずしも内容が一致しません。宗教法人会計と税務収益事業会計との関係を図説すると、次のとおりです。 ●宗教法人の区分会計(経理)と税務収益事業 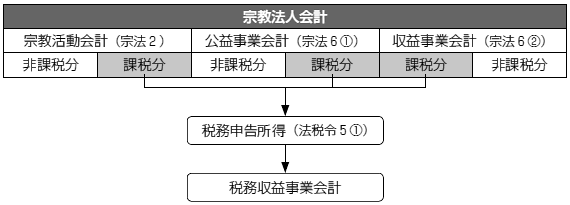 ◎収益事業課税における不文の概括基準の活用 法人税法は、収益事業(以下「税務収益事業」ともいいます。)とは、「収益事業、販売業、製造業その他政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいう。」としています(法税法2十三)。そのうえで法人税法は、どのような事業が課税対象となるかについては「限定列挙主義」「特掲主義」を採っています。現在、34業種を特掲しています(法税令5)。 宗教活動か収益事業か、収益事業にあたるとすればこれら34業種のいずれにあてはまるのか、の課否を問われたときに課税庁は、不文の概括基準や概括原則を適用する傾向を強めています。こうした基準や原則を適用することにより、「宗教活動」に対する課税権の行使を積極化させているわけです。 こうした基準や原則のうち主なものとしては、「対価 対 寄附(喜捨)基準」や「イコール・フッティング論」を挙げることができます。 (1)「対価 対 寄附(喜捨)基準」とは 宗教法人は、「宗教的側面」ないし「聖」の面と、「世俗的側面」ないし「俗」の面をあわせ持った法人です。憲法が保障する政教分離原則(憲法20)のもと、宗教法人の宗教活動、つまり「聖」の面に対する課税権の行使は抑制されなければなりません。宗教活動非課税制は、そうした趣旨で採られている仕組みです。 しかし、従来から税務収益事業の課否判定においては、「宗教活動」に係る物品やサービスであっても、それが「対価(compensation)」の支払において提供されたのか、あるいは「任意の寄附金・喜捨金(voluntary donation)」なのかを基準(以下「対価 対 寄附(喜捨)基準」という。)に判断する傾向を強めています。 対価 対 寄附(喜捨)基準のような不文の概括基準は、具体的には、“宗教法人のペット葬祭は宗教活動か収益事業〔請負業など〕か”といったケースで課否判定に適用されています。課税庁は、この基準を適用することにより、実質的に「宗教活動」、「聖」の面に対する課税権の行使を積極化させているわけです。言い換えると、税法の執行(税法の適用・解釈)において安易に、対価 対 寄附(喜捨)基準を持ち出して課税することについては、宗教活動非課税制をないがしろにすることにつながるのみならず、租税法律主義、その派生的な原則である課税要件明確主義にも抵触すると解されます(1.1.1)。 (2)イコール・フッティング論とは 課税庁は「宗教活動」に対する課税権の行使を積極化させるため、「民間企業との競争条件の対等化」、つまり「イコール・フッティング(equal footing)」の論理を持ち出すようになっています。 “宗教法人のペット葬祭は宗教活動か収益事業〔請負業など〕か”が問われたケースで課税庁は、宗教法人の活動が民間事業者と同じである以上、イコール・フッティング論に基づき、民間事業者と同等に課税されるべきであると主張しています。 不文の概括基準の一つであるイコール・フッティング論は、本来、立法上の原理(principle for legislative resolution)です。税務執行や司法の場において税法の適用・解釈上この論理を持ち出すことは、あたかも同じく立法上の「租税負担公平の原則」、あるいは税法の解釈・適用上の原理とされる不文の「実質課税の原則」などを持ち出すに等しいわけです。 税法における基本原則は、憲法に定められた租税法律主義です。この原則は、租税の賦課・徴収は必ず法律の根拠に基づいて行われなければならないというルールです。 一般事業者がペット葬祭の分野へ参入してきたから、税法に明確な定めがないのにもかかわらず、イコール・フッティング論を根拠に、宗教法人にも一般事業者と同様に課税することにするというのは、あまりにも乱暴です。税法の執行(税法の適用・解釈)においてイコール・フッティング論を持ち出すことについては、宗教活動非課税制をないがしろにすることにつながるのみならず、租税法律主義から導き出される課税要件明確主義に反すると解されます(1.1.1)。 ◎通達による収益事業課税の問題とは 課税庁は、「対価 対 寄附(喜捨)基準」や「イコール・フッティング論」のような不文の概括基準を使い、さらにはこうした概括基準や概括原則を事例化した税務通達で、収益事業の課否判定を自在に行っています。 収益事業関係の税務通達では、まず、宗教法人が伝統的に宗教活動として行ってきた業務であっても、税務収益事業にあてはまれば法人税がかかるルールを打ち出しています(法税基通15−1−1、15−1−10等)。宗教法人の「聖」の面への課税を認めることにつながっているわけです。 反面、収益事業にあたる場合であっても、墳墓地の貸付け(法税基通15−1−18)や宗教法人の有する宿泊施設に信者や参詣人を1泊1,000円(2食付きで1,500円)以下の料金で宿泊させる場合には税務収益事業(この場合は旅館業)にあたらないとし(法税基通15−1−39、15−1−42)、法人税がかからないこともあります(法税令5 こうした課否判定の典拠となっている法人税法基本通達は、国税庁長官が発遣しています。法的な性格は、国税庁長官が国税局や税務署およびその職員の職務に対して、法令の解釈や執行・運営方針などを指示・徹底するために出す文書です。したがって、対納税者間では必ずしも法的拘束力(法源性)を有しないものです。ところが、現場の税務職員はこの税務通達に従って仕事をするために、納税者も間接的に通達に縛られることになるわけです。税務通達は法源性を欠くことから、通達課税は、租税法律主義の要請に対する大きなインパクトになります※。 現在の対価 対 寄附(喜捨)基準のような概括基準や税務通達を幅広く活用した収益事業課税のあり方については、「課税は法律に基づいて行う」という憲法の租税法律主義の原点に立ち返って精査する必要があります。また、とりわけ宗教法人に対する収益事業課税のあり方については、憲法が保障する政教分離原則のもと、宗教法人の「宗教的側面」、「聖」の面、つまり“「宗教活動」に対する課税権の行使は抑制されなければならない”という原点に立ち返って精査される必要があります。 「宗教活動」への課否が問われた場合、概括的な対価 対 寄附(喜捨)基準を使い、法解釈により収益事業課税の範囲を決める動きは、これら行政(課税庁)のみならず、司法(裁判所)でも積極化する傾向にあります。例えば、宗教法人の行うペット葬祭施設は非課税の宗教施設か、宗教法人の行うペット葬祭は宗教活動かが争われたケースでは、対価 対 寄附(喜捨)基準に基づいて判決が下されています。こうした司法の動きにも注目する必要があります。 (石村耕治)
|